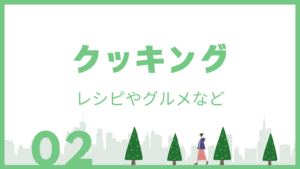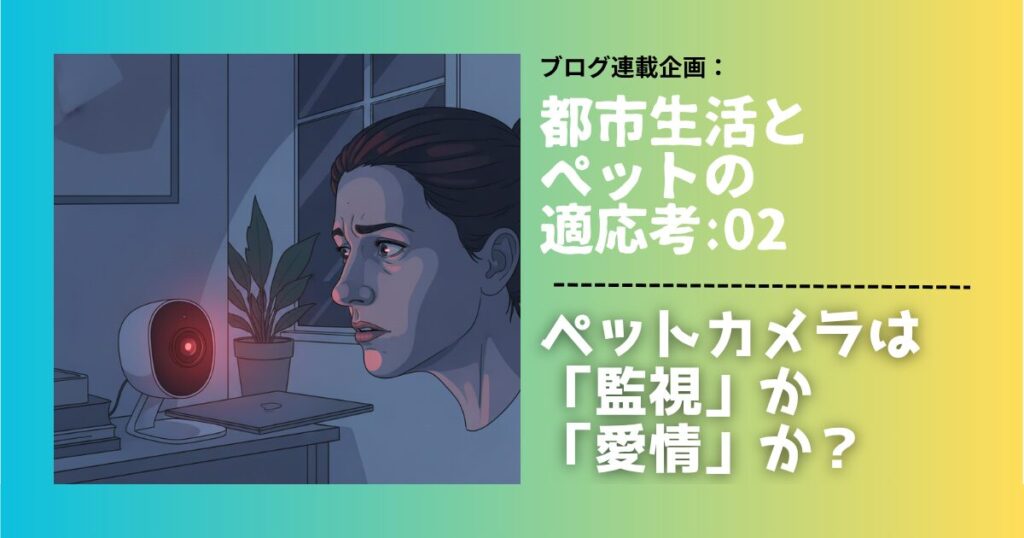
目 次
第1章:導入と「人間の不安」の具現化
前回のテーマは、集合住宅の「音」という物理的な問題でした。
今回は、現代の飼い主が抱える精神的な不安にテクノロジーがどう介入しているか、「見守りカメラ」を中心に考察します。
ペットを家族として迎えたからには、留守番中の安全を確保したい。
この強い愛情が、カメラやIoTデバイスという形で具現化し、私たちはペットの「居場所」を24時間遠隔で設計できるようになりました。
しかし、この便利さは真の安心でしょうか?
私は、このデジタルな繋がりが、時に「監視疲れ」という新たなストレスを生んでいるのではと感じています。
第2章:見守りカメラの「功罪」:カメラが設計する居場所

カメラは本来、物理的に離れた飼い主とペットを「繋ぐ」ツールです。
その最大の功績は、緊急時の事故防止や、病気の早期発見といった安全管理の設計にあります。
特に高齢のペットや病気のペットを飼う家庭では、生命維持のための重要なインフラです。
一方で、カメラは飼い主に「常に見ていられる」という心理的な負荷を与えないでしょうか。
外出先で何度もアプリを開き、ペットが眠っているだけの映像を見て安堵する。
これは、カメラが「留守番中のペットの状態を確認しないと不安になる」という新たな行動パターンを飼い主に設計しているとも言えます。
実際、ペットが家族で、そこに人格(ペット格)があるとするとどうでしょう。
子供部屋を24時間カメラで覗きはしないことを思うと、果たしてこれはいかがか? もとい、ペットとの関係を再考しなくてはいけないと思うのですが……
さらに、カメラの「死角」は、住宅設計者にとって興味深い問題です。
死角はペットのプライベートな空間を守る一方で、飼い主にとっては「不安の領域」として残ります。
テクノロジーの進化は、この死角をなくそうと広角化や追尾機能を取り入れますが、ペットにとっては「逃げ場のない空間」になりかねません(と自覚しているかどうかはわかりませんが……)。
これを遠隔地にする老母や老父のこととして思うと、複雑な気持ちになり、結論を先送りしたくなるのは私だけでしょうか。
第3章:IoT給餌器・自動トイレの「効率化」と動線デザイン

見守りカメラと並び普及が進むのが、自動給餌器や自動トイレといった「IoTデバイス」です。
これらは、人間の手間を最小限に抑え、生活を「効率化」するために設計されています。
そのためか、思った以上に普及し始めているようです。
建築設計において、キッチンや洗面所の効率的な動線設計は重要ですが、IoTデバイスはペットの動線を再設計します。
例えば、設定された時間に正確に餌が出る自動給餌器は、ペットの体内時計をプログラムし、人間の介入なしにルーティンを確立させます。
しかし、注意したいのは「配置」です。
自動給餌器をリビングの隅に、自動トイレを玄関先に無造作に置くことは、単に「物を置く」という行為で終わってしまいます。
設計の視点から言えば、これらのデバイスは、ペットが安心して食事、排泄、休息を取れる「テリトリー」の中心に位置づけるべきです。
カメラで確認できる場所、他の家具からの視線を遮れる配置、床材のメンテナンス性まで考慮に入れた「IoT動線」の設計が不可欠なのです。
しかし、実際はなかなかペットのご希望や習慣を把握するのは難しく、クライアント(人間)の意向に全面的に従うこととなります。
第4章:テクノロジーの限界と「人間の存在」の設計
私たちはカメラ越しにペットを見て、まるで傍にいるかのように錯覚します(のはず……)。
しかし、デジタルツールはあくまで「情報」を提供してくれるだけで、温もりや匂いといった「存在」の代替にはなり得ません。
犬や猫は、ただ餌をもらって清潔な場所で眠るだけでなく、飼い主の特定の匂いや体温、声といったアナログな情報を求めています。
テクノロジーが発達すればするほど、飼い主は意識的にペットとの物理的な時間やコミュニケーションの機会を「設計」しなければならないのです。
便利なツールを最大限に活用しつつも、それらがない時間、オフラインの空間での濃密な触れ合い。
それが、現代の都市生活におけるペットとの共存の最も重要な設計要素だと、私は考えます。
そういえば、たまごっちがまた流行っているようです。
関連記事
低カロリーでも食いつき◎モグニャンライトがシニア猫に選ばれる理由
年齢とともに運動量が減り、体型が気になる猫ちゃんに。低カロリーなのに美味しい「モグニャンキャットフードライト」をご紹介。グレインフリーでシニア期の健康もサポートする、愛猫と飼い主の願いを叶えるプレミアムフードの魅力に迫ります。
HARIOのペット用品で変わる!犬猫との快適な暮らし
老舗メーカーHARIOのペット用品は、人間用の食器製造で培った技術を応用し、ペットの体格や悩みに合わせた設計が特徴。おしゃれなデザインと高い機能性で、愛犬・愛猫との暮らしを豊かにします。
ペット火葬で後悔したくない方へ。東京の訪問火葬サービスをご紹介
大切なペットとのお別れ、後悔なく見送るためにはどうすればいい?この記事では、東京で安心して利用できる「おみおくりペット火葬」のサービス内容と、納得できるペット火葬を選ぶためのポイントをご紹介します。